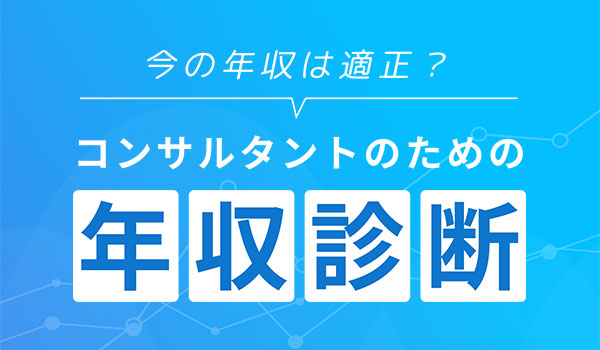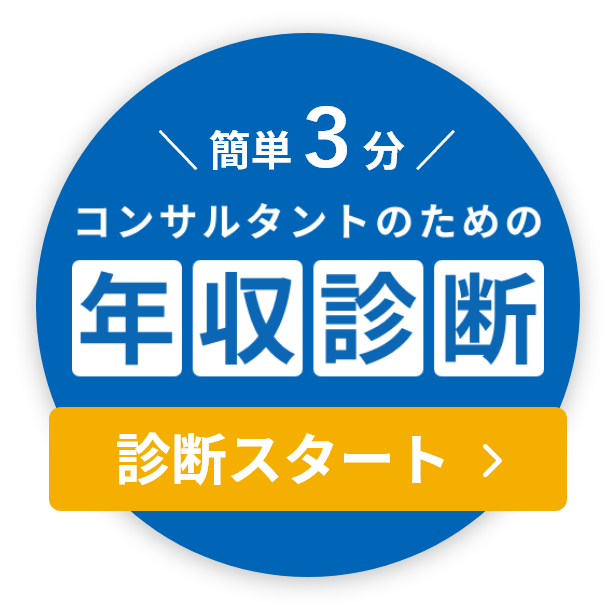コンサルタント転職の受かる志望動機書・履歴書・職務経歴書の書き方

コンサルに限った話ではありませんが、履歴書や職務経歴書といった書類選考は、転職の最初の関門です。
応募書類を作成するにあたっても、漫然と書くのではなく、書類ごとに求められている要件を把握し、そこから逆算して準備する必要があります。
ここでは、書類対策の基本からコンサル転職ならではの注意点まで、応募書類(履歴書・職務経歴書・志望動機書)のポイントについて解説します。
1.受かるコンサル志望動機の書き方

志望動機書には、志望動機を伝えることによって、採用側から自分が採用する価値のある人材であると思ってもらうという明確な目的があります。
ありのままの志望動機を伝えるために書くのではなく、他の候補者より魅力的で、かつ自分が業務に貢献できるということを証明するために書くと言えるでしょう。
1)コンサル志望動機を書くときに押さえておきたい3つのポイント
①どうしてコンサルがやりたいのか?
志望動機を書く際にはなぜコンサルタントになりたいのかという明確な理由が必要です。特にコンサル業界は論理性を求められるため、コンサルタントになりたい理由についても面接官が納得するような明確な理由付けが必要となります。そのためには、まずはコンサルタントの仕事内容を理解し、今の仕事とどのようなつながりがあるのかを明確にすることが重要です。コンサル業界の転職に限らず、現職の仕事内容をどのように活かせるか明確に話せるようにしておくことで選考突破率は大幅に上昇します。コンサルタントになりたい理由を自分なりに組み立て、様々な角度から想定問答を準備することで面接でも緊張せずに受け答えできるでしょう。
②どうしてこの会社なのか?
志望動機において次に重要なのが、どうしてこの会社を選んだのかという理由です。後述の通り、コンサル業界には総合系、戦略系など様々なカテゴリが存在し、それぞれに特色があります。そのため、同じコンサル業界でも、企業によっては自分が本来持っていたイメージと全く異なる仕事内容である可能性があります。そのため、コンサルタントになりたい理由と同様になぜこの会社なのかという質問に対しても論理的に組み立てられた答えが必要です。企業のWEBサイトから過去のプロジェクト事例を確認する、転職エージェントに質問してみることなどを通して、志望する企業の仕事内容を具体的にイメージして、どうしてこの企業なのか自問自答するとよいでしょう。
\ハイパフォキャリアへのご相談はこちらから/
③どう貢献できるのか?
コンサル業界では特定の商品を提供するわけではないため、プロジェクトを通して作成された報告書や資料などが成果物(アウトプット)として重視されます。つまり、一人のコンサルタントがどのような成果を出せるのかについて厳しく評価されるのです。そのため、面接においても必ずと言っていいほど自社に対してどのような貢献ができるかについて質問されます。この質問に対しては、現職の経験がどのように業務に生かせるのかを根拠をもって説明することが求められます。仮に異業種からの転職であっても、何らかの共通点があるはずなので、現状の経験が入社後にどのように生かされるのか、再現性があるのかについて重点的に説明するようにしましょう。
2)コンサル志望動機のNG例&注意点
【NG例】
今の職場では、会社の制度上与えられたものをこなすだけで、責任のある仕事を任せられず、常々不満を覚えておりました。また、年功序列制度が根強く残り私の出した成果が正当に評価されない環境だと考えています。そのため、貴社のコンサルタントになることによって、風通しがよく実力主義の環境に身を置きたいと考え貴社を志望しました。
【改善に向けた注意点】
上記のNG例における注意点は2点です。まず、現状の環境に対して改善しようとする努力が見られないことです。転職にあたっては現職への何らかの不満があることは面接官も理解していますが、改善への努力が見られない場合、問題解決能力が低いと捉えられかねないですし、また別の理由で辞めてしまうのではないかと考えます。そのため、現職への不満があった場合でも例えば、「業務フローの改善提案を試みたが、解決されなかった」というところまで具体的に説明できると良いでしょう。
もう一つのポイントは、コンサルタントになりたい理由が希薄であることです。コンサル業界には風通しがよく実力主義の企業は多数あるため、この志望動機ではなぜコンサルになりたいか、どうしてこの企業を志望したのかが全く見えてきません。
コンサルティングファームの選考において、特に未経験の場合は「コンサルタントになりたい明確な理由」が非常に重要です。そのため、「現職で培った論理的思考力をクライアントの業務改革において発揮したい」などの「コンサルタントになりたい明確な理由」を企業にアピールすることが重要なポイントになります。
3)【種類別】コンサル志望動機の例文5選
例文①総合系コンサルティング
【例文】
貴社を志望した理由は、現職のITベンダーにおけるソリューション営業の経験を貴社が強みとするIT戦略策定コンサルティングの場で活かしたいと考えたからです。私は現職で営業として売上を拡大すると同時に、クライアントのIT部門と並走して中長期計画策定に関わってきました。そのため、クライアントとの関係構築を始め、顧客視点で最適なソリューションを提案することができます。貴社でIT戦略策定コンサルティングに携わることで、現職よりも広い業界のクライアントに対してIT戦略の策定と実行支援を行い、日本全体のDXに貢献したいと考えております。
【ポイント】
近年は企業の事業戦略にITが欠かせないものになっており、IT系と総合系の垣根が小さくなっています。そのため、従来よりもITの知見がある人材が優遇される傾向が強まっています。そのため、志望動機には戦略立案に関わった経験などに加えてITに関するアピール要素を含めるとよいでしょう。
例文②戦略系コンサルティング
【例文】
貴社を志望したのは、現職のマーケティング部で従事している海外マーケット開拓の業務経験が、貴社が展開するマーケティング部門へのコンサルティングで活かされると考えたからです。現職では北米支社と現地でのシェア拡大に向けた施策や方向性について、様々なデータに基づいた議論を行い、3年間で現地でのシェアを10%上げることができました。この経験から今後人口減少により市場が縮小していく日本から海外に活路を見出す企業を幅広く支援したいと考えるようになり、貴社のマーケティング部門向けコンサルティングを志望しました。
【ポイント】
戦略系コンサルティングでは大量にあるデータの中から、解決すべき課題を抽出し、論理的な解決策を組み立てる必要があります。そのため、論理的な思考に基づいて定量的な成果を出してきた人材が好まれます。
例文③IT系コンサルティング
【例文】
私は現職のシステムエンジニアの業務で培った経験を、貴社が今後拡大しようとしている製造業向けDXコンサルティングの領域で生かしたいと考えて貴社を志望しました。現職ではシステムの設計やプログラミングといった経験を積んで参りましたが、より上流の工程にチャレンジし企業全体のDXに貢献したいと考えたことも貴社を志望した理由です。また、現職では一貫して製造業のクライアントに関わるプロジェクトを経験してきましたので、製造業における業務の仕組みについても深く理解しています。これまで培った技術と業務的な知見により、貴社コンサルタントと実際に開発に関わるシステムエンジニアとの橋渡し役としてコミュニケーションを行い、プロジェクトを円滑に進めることができると考えております。
【ポイント】
IT系コンサルティング企業では、クライアントのIT投資計画策定やシステム開発の要件定義といった上流工程の仕事に加えて、設計やプログラミングなど下流の工程に関わることも増えています。そのため、コンサルティングの経験がなくとも、システムエンジニアやプログラマーの経験がある人材を求める傾向があります。
例文④シンクタンク系コンサルティング
【例文】
私は現職の国家公務員における少子化対策の政策立案経験を、日本社会の中長期的な成長を目指す貴社のビジネスで活かせるのではと考え志望しました。現職では30~50年後の持続可能な社会を実現するため、中長期的な政策立案に携わり、データの収集・分析、多方面との調整や折衝を行って参りました。その中で、少子化の解決は短期での利潤を追求せざるを得ない民間企業だけの努力では難しいと感じ、元公務員の知見を活かし、政府機関に対して中長期的な政策提言を行う貴社の業務に携わりたいと考えております。
【ポイント】
シンクタンク系のコンサル企業は、中長期的なスパンで少子高齢化環境問題といった社会課題に対する分析や課題解決を行うことが、他のコンサル企業との大きな違いです。そのため、なぜ他のコンサル企業ではなくシンクタンクなのかといった違いは明確にしやすいといえるでしょう。
例文⑤組織・人事コンサルティング
【例文】
貴社を志望する理由は、現職の人事部における採用業務効率化の経験を活かして人手不足に悩む企業の課題を解決したいと考えるためです。一部の大企業を除き人事部の業務は少人数で実施されていることが多いため、特に中小企業では目の前の業務に追われて中長期的な視点での人材採用ができていないと認識しています。現職での経験に基づいた効率化のコンサルティングを行うことで、人手不足に悩む企業を少しでも減らしたいと考えました。貴社が手掛けている中小企業向け採用業務のコンサルティングは、まさに私の目標に合致しており、入社した暁にはやりがいをもって働けると考えております。
【ポイント】
組織・人事のコンサルにおいては、やはり企業の組織改革や人事部での経験がある人材が好まれます。特にクライアントが企業の人事部になることが多く、クライアント視点でのコンサルティングが求められることから、現職で類似の経験があれば全面的にアピールするとよいでしょう。
2.受かるコンサル職務経歴書の書き方
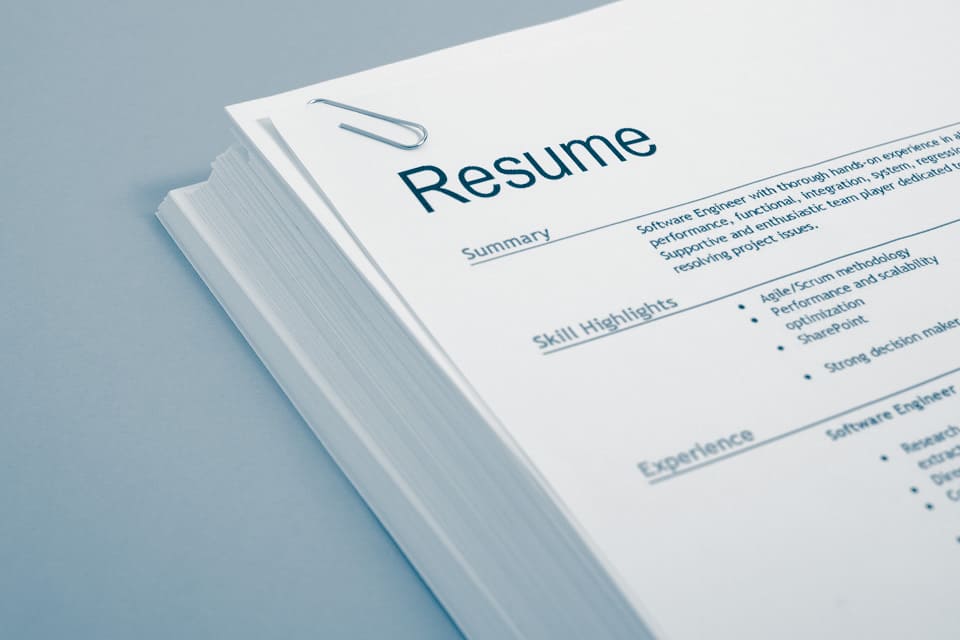
1)コンサル職務経歴書の書き方
職務経歴書は2~3枚程度が理想です。冒頭に「職務概要(サマリー)」、次いで職務経歴ごとに「スキル/得意分野」「職務内容の詳細」を書きます。
まず、職務概要を2〜3行程度で記載します。概要なので、これまでの職務経歴の流れを簡潔に記します。その後に、職務経歴ごとにスキルや職務内容の詳細を、過去に在籍した企業の数だけ記入していきます。
ただし、どの職務経歴も同等の扱いとするのではなく、今狙っているコンサルのポジションとの関連が深い職務経歴と、そうではない職務経歴で、記述の詳細さを変えて強弱を付けます。
重要なのは、自らのブランディングに役立つ部分を重点的に書くことにより、積極的に加点を取りに行くということです
職務経歴書は、過去の職歴や業務内容、成果などを通じて、自らの訴求ポイントをアピールして積極的に加点を狙うものです。商品としての自分自身をブランディングするためのものなので、明確な戦略が必要です。
職務経歴書を通じてチェックされるのは、求職者がコンサルタントの業務に求められる能力を満たしているかどうかです。
書類選考を通過しなければ面接のステップには進めません。自分自身が人事担当になったつもりで、この職務経歴書はどう映るかという観点で作成しましょう。また、作成した職務経歴書は、必ずエージェントのチェックを受けておきましょう。
ハイパフォキャリアでは、コンサルティング業界に精通したコーディネーターによる書類選考を突破するための徹底した添削や、各社の特徴を踏まえた徹底対策を行います。 コンサルティング業界への転職を希望されている方は是非ハイパフォキャリアのコンサルタントへご相談ください。
2)コンサル職務経歴書を書くときの3つのポイント
①問題解決力・課題解決力をアピール
コンサル職務経歴書の作成で重要なのは、問題解決力や課題解決力をアピールすることです。 問題解決力や課題解決力は、コンサルタントに求められる能力のうち最も重要ですので、どういった思考プロセスで問題や課題を解決したのか具体的に記載できるとよいでしょう。
②実績はなるべく定量的に
コンサル職務経歴書において、実績をアピールする場合は、なるべく定量的に表現することがポイントです。「売上が大幅に向上」→「売上が前年同月比で80%増」、「トップクラスの成績」→「全社で上位3%の実績」などというように、具体的な数字で示すとよいでしょう。 「職務内容の詳細」では、自らの担当業務を記述するだけではなく、ご自身がチームの一員として参画することにより、どのような変化(Before/Afterの課題と成果)があったのか、業績やチームへの貢献度をわかりやすく説明するのがポイントです。
③簡潔にわかりやすく整理
コンサル職務経歴書を書く際は、簡潔にわかりやすく整理するようにしましょう。 コンサル業界は、資料作成をする場面が多数存在するため、職務経歴書を通して、ポイントを分かりやすく整理して伝える資料作成ができる人材かどうかを見ています。 中でも、最も重要なのは冒頭のサマリーで、どんなに忙しく、書類全体に目を通す時間の無いコンサルティングファームの面接官も、冒頭のサマリーだけは目を通すため、作成した職務経歴書は簡潔にわかりやすく整理されているかを今一度確認するとよいでしょう。
3)コンサル職務経歴書を書くときの注意点
1-1)書き方の注意点
基本的なことですが、誤字脱字には注意してください。いったん完成したら、一度必ず紙にプリントアウトして、赤ボールペンを片手に、PC画面で見るのとは違った目でチェックするのがおすすめです。
また、文章の言い回しには、知的な表現やフォーマルな単語を使い、稚拙な表現やくだけた表現は避けましょう。職務経歴書では、書かれている内容だけではなく、文章構成能力そのものも見られているからです。
なお、職務経歴書において、コンサルティングファームの募集ポジションによっては、面接前の足切りポイントが存在する場合があります。 たとえば、戦略系コンサルティングファームでは、学歴や職歴がチェックポイントになる場合があり、総合系コンサルティングファームでは、募集部門の業務経験だけでなく、IT経験や、PM経験等の有無が、採用の判定基準として設定されている場合もあります。
このあたりの実情については、採用側の内情に詳しいエージェントから、アドバイスを得ておくとよいでしょう。
ハイパフォキャリアでは、コンサルティングファームとの太い情報パイプを活かし、ネット検索では出てこないコンサルティングファームの重要かつリアルな情報をご提供可能です。
コンサルティング業界への転職を希望されている方は是非ハイパフォキャリアのコンサルタントへご相談ください。
1-2)内容面での注意点
職務経歴書は自分が今持っている経験をアピールする上で非常に重要な書類です。そのため、簡潔な記載を心がけつつも、必要なアピール要素はもれなく含める必要があります。職務経歴書において自分の経験をアピールする際には。注意点が2つあります。一つ目は、アピールしたい要素は具体的かつ定量的に記載することです。例えば、営業職での経験を書く場合は前年比や目標に対する達成率といった定量的な指標で自分の出した成果をアピールするとよいでしょう。営業職と違い具体的な数字が出にくい業務であっても、業務効率化の実績など定量化できる部分があるはずですので自分の経験を掘り下げて考えてみましょう。定量的な指標を用いることでより説得力のあるアピールが可能になります。二つ目の注意点は、周囲を巻き込んだエピソードを含めることです。多くの場合、業務上の成果はチームで成し遂げたものでるはずです。現職での成果についての記載があまりにも独りよがりであると、協調性の欠如を疑われてしまうので、成果をアピールする際にはどのように周囲を巻き込んだか、どのようなサポートを受けたのかについても記載するとよいでしょう。
4)コンサル職務経歴書のサンプル
職務経歴書
2022年10月31日現在
氏名 XX XX
■活かせる経験・知識・技術
前職のA社では、自社開発のパッケージソフトの開発に従事し、Javaを用いたプログラミング、小規模な開発チームのマネジメントを経験した。2015年以降はシステムの要件定義を始めとした上流工程の業務にも従事した。2017年に現職に転職して以降は、大手自動車メーカー向けのポータルサイト開発プロジェクトに参画し、ポータルサイトの基盤となるクラウド環境の構築に携わった。ポータルサイトの稼働後はクライアントに対して継続的なシステム改善提案を実施している。
■職務要約
・Javaを使ったシステムの設計、開発(プログラミング)
・Microsoft Azureを使ったクラウド環境の構築
・製造業における業務フローの理解
・小規模なチーム(3-4名程度)のマネジメント経験
・要件定義を始めとした上流工程の経験
・システムの改善提案
■職務経歴
資本金:1千万円(2022年3月) 売上高:10億5千万円(2022年3月)
従業員数:800人 上場:未上場
●2013年5月~2015年3月
<主なプロジェクト>
・中小企業向け生産管理パッケージの開発プロジェクト
<開発環境>
OS:Linux
DB:Oracle Database
開発言語:Java
<職務の詳細>
自社で販売する中小企業向け生産管理パッケージの機能追加に向けた開発メンバーとして。Java言語を用いたプログラミングに従事した。周囲のサポートを得ながらも約半年で1人月に相当するペースでコーディングが進められるようになり、2014年度からは小規模な開発チーム(メンバーは協力会社を含め3-4名程度)のリーダーを務め、自らも開発に携わりつつ、チームのマネジメントも行った。プロジェクトの途中では、バグの発生により進捗が思うようにいかない部分もあったが、チーム内での手順書整備、ノウハウ共有会の開催などを通じた品質改善の取り組みを行い、結果的に遅延なく開発を完了させた。
●2015年4月~2017年3月
<主なプロジェクト>
中小企業向け経理システムの要件定義・設計を担当
<開発環境>
OS:Windows 2000
DB:PostgreSQL
開発言語:Java
<職務の詳細>
先述した中小企業向け生産管理パッケージのプロジェクトで得た経験をより上流の工程でも生かしたいとの思いから、プロジェクトの異動を希望し、中小企業向けの経理システム開発プロジェクトに参画し、システムの要件定義と設計を担当する。上流工程では従来のシステム開発では意識していなかった、システム化の対象となる業務の流れについて深く理解することが求められ、最初の内は周知に質問しながら進める状況が続いた。自身でもクライアントについて深く調査して理解するなどの取り組みを行った結果、クライアントとの定例会でも質問に対してスムーズに回答できることが増え、クライアントからの信頼を徐々に勝ち取っていった。
資本金:1億円(2022年3月) 売上高:1,100億円(2022年3月)
従業員数:10,000人 上場:東証プライム上場
●2017年4月~現在
<主なプロジェクト>
・大手自動車メーカー向けポータルサイトの設計・開発プロジェクト
<開発環境>
OS:Windows
DB:PostgreSQL
開発言語:Java
<職務の詳細>
より大きなクライアントを相手にしたいとの思いから現在の会社に転職し、大手自動車メーカー向けポータルサイトをクラウド上に構築するプロジェクトに参画した。当初の業務は前職の経験を活かしたJavaのプログラミングが中心であったが、人的リソース不足の問題から未経験であるクラウド環境構築の業務に従事した。当初は不慣れな点が多く、思うように進められないこともあったが、自己学習と有識者からの支援により、結果的には遅れることなくポータルサイトの土台となる環境を整備することができた。システム稼働後は、ポータルサイトをより使いやすくするための改善業務にも携わり、クライアントのニーズを把握した提案を数多く行った。
■資格
普通自動車第一種運転免許(2012年1月)
基本情報技術者(2014年9月取得)
TOEIC 750点(2021年6月取得)
■自己PR
達成したいゴールから逆算した目標設定を行い、緻密にプロジェクトを進めていくことに強みがあります。目標達成の過程で予期せぬ事態が発生した際も、周囲との丁寧なコミュニケーションをとりつつ、的確に課題を把握し迅速な軌道修正を図ることができます。また、現職で従来から得意としていたJavaを用いたプログラミング、システム設計に加えて、クラウド上での開発環境の構築に携わったことにより、システムインフラについての知見も身につきました。このように複数の分野を横断的に経験したことにより、技術者としてのみならず複数のチームの橋渡しとして、プロジェクト推進を円滑に進めることができると考えております。さらに、継続的なシステム改善提案を続ける中で、論理的かつわかりやすいプレゼンテーションを心がけ、実際に多くの提案を受け入れていただくことができました。
3.受かるコンサル履歴書の書き方

1)コンサル履歴書の書き方
JIS規格のフォーマット(WordまたはExcel)を利用してPCで作成するのが基本ですが、手書き指定がある企業は手書きで記載します。 ただし、コンサルティング業界への転職においては、手書き書類の提出を求められることはほとんどありません。 「休学」「留年」などは、一見マイナスなイメージですが、隠すことなくその明確な理由を明記します。(海外留学等)
2)コンサル履歴書を書くときの3つのポイント
①履歴書はフォーマット通りに簡潔に
履歴書は積極的に加点を狙うというよりも、記載ミスや内容の矛盾による余計な減点を避け、自分自身に関する事実について、フォーマット通りの記述を簡潔に行うことが大切です。そのため、特に以下のポイントに注意しつつ作成するようにしましょう。
- ・学歴・職務経歴の年月にズレや矛盾が発生しないように記述する
- ・学歴や経歴の詐称は絶対にしない
- ・誤字脱字はゼロになるまで見直しをする
上記のポイントを満たしていないと、ビジネスマンとして備えているべき基本的なドキュメント作成能力や注意力が疑われ、明確に減点要素となりますので、細心の注意が必要です。履歴書は、失点につながらないようにまず間違えないこと、それを念頭に作成しましょう。
②語学力をアピール
コンサル業界では海外とのやりとりが頻繁に発生する企業もあるため、英語力が高いことは明確なアピール要素です。また、コンサル業界には外資系企業も多いため、海外本社とのやりとりで英語力が求められるケースもあります。TOEICやTOEFLで高得点を取得している方は、履歴書の資格欄に記載することで書類選考の通過率を上げることができるでしょう。
一方で、TOEICやTOEFLのスコアを取得しているものの、高いスコアではない場合はアピール要素にはならないため、履歴書に記載しないことをおすすめします。もし、語学力について面接で確認された場合は今後学習を進めていく予定であることなどを話し、語学力についても向上の意思があることを示しましょう。
③コンサルとの関連がない資格はあえて記載しないのが無難
現状で保有している資格については、コンサルタントの業務に活かせるものや、業務に関連するものに絞って履歴書に記載します。一般的な普通自動車免許や、カラーアドバイザーなど、コンサル業界との直接的な関連がなく、趣味の要素が強いものは、あえて記載しなくてもよいでしょう。また、転職後の業務に関連がなくとも現職の成果として取得した資格については、自身の努力をアピールするために記載することも一つの作戦です。
ただし珍しい資格を有している場合は、面接におけるアイスブレークに役立つ場合があるため、明確な意図をもって履歴書に記載する場合もあります。実際に資格に関する記載をどのようにするかについては、転職エージェントの意見を聞きながら方針を固めていくとよいでしょう。
\ハイパフォキャリアへのご相談はこちらから/
3)コンサル履歴書を書くときの注意点
1)書き方の注意点
コンサル業界では形式を問わず資料作成をする場面が多数存在します。そのため、履歴書を通して正確な資料作成ができる人材かどうかを見ており、履歴書が書類選考における足切りポイントになる可能性があります。
しかし、コンサル業界であるからといって履歴書に特別な対策が必要なわけではありません。先述の通り、学歴や職歴の欄に記載する年代に矛盾を発生させない、ビジネスマナーに即した書き方ができているか確認する、誤字脱字がないようにプリントアウトしてチェックするなど、基本的な部分を忠実に実践して間違いのない履歴書を作成しましょう。コンサル業界に限りませんが、履歴書作成時によくある間違いは以下の通りですので、事前に確認しミスの防止に役立ててください。
【履歴書作成時のポイント・注意点】
- ・和暦と西暦を混在させない。
- ・転職が多い場合はこれまでの経歴に過不足がないかを確認する。
- ・卒業した学校や退職した名称が変わっていないか確認する。
- ・誤字脱字は少し時間をおいてから確認する。
- ・取得した資格に有効期限がある場合は失効していないかを確認する。
1-2)内容面での注意点
コンサル業界に転職するための履歴書作成においては、書き方と同様に内容面も基本に忠実に記載することが重要です。履歴書はあくまでも自分自身の経歴に関する事実をシンプルかつ正確に伝えるためのものですので、コンサル業界においても特別な対策は必要ありませんが、資格欄の記載に関しては工夫の余地があります。先述の通り、資格欄には業務に直結する資格を記載することが前提となります。
ここでは具体的な例をいくつか紹介しましょう。もし監査法人を前身とするコンサル企業に転職するのではあれば、簿記検定など会計に関する資格が有利に働くことがあります。また、IT系コンサルティング企業であれば基本情報技術者試験などに合格していればITの知見があることが示せますし、PMP(Project Management Professional)やプロジェクトマネージャーの資格を持っていればプロジェクトマネジメントの能力をアピールできるでしょう。
また、TOEIC、TOEFL、英検といった語学に関する資格は、どのコンサル企業を受験する際にもプラスになるでしょう。職務経歴書に加えて、履歴書の資格欄においても自身の経験や能力をアピールできることがあるため、資格を持っている方は大いに活用することをおすすめします。
4.まとめ
各書類には、書類ごとの目的や、選考の一環として、書類のどの部分をどのように見られているかといった要件が存在します。
どの書類も、自分の提供できる価値をコンサルティングファームに訴求するという点では目的が一致しており、その表現方法が、履歴書・職務経歴書・志望動機書でそれぞれ異なるに過ぎません。
書類作成に入る前に、ご自身の経歴やスキルセット、転職を今のタイミングで考えるに至った背景などについて、まず情報整理をしておきましょう。
このようなリサーチや分析を元に書類を作り込んでいくというのが、コンサルティングファームにおける書類作成のポイントです。
上述した通り、コンサルティングファームの選考において、書類作りは重要なので、不安がある人はコンサルティングファームに特化したエージェントに相談することをおすすめします。
\ハイパフォキャリアへのご相談はこちらから/
転職ノウハウ記事一覧
- 1.コンサルタントなら知っておきたい転職の流れ・選考プロセス
- 2.コンサルタント転職の受かる志望動機書・履歴書・職務経歴書の書き方
- 3.【コンサル転職】適性検査・Webテスト対策まとめ
- 4.【コンサル転職】面接対策まとめ~流れから逆質問対策まで詳しく解説!
- 5.ケース面接とは?~対策方法やフェルミ推定についても詳しく解説!~